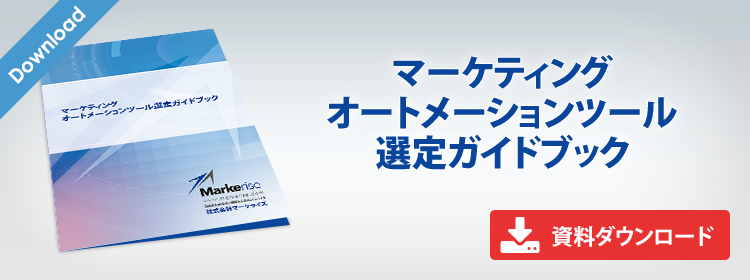顧客行動をコントロールできる?「心理トリガー」で効果的なマーケティングを!
心理トリガーの活用は有効なマーケティング戦略の一つですが、その活かし方を詳しく知らない方は多いかもしれません。この記事では、心理トリガーとは何か解説したうえで、心理トリガーを活用した効果的なマーケティング施策をご紹介します。

この記事の目次
心理トリガーの活用は有効なマーケティング戦略の一つですが、その活かし方を詳しく知らない方は多いかもしれません。この記事では、心理トリガーとは何か解説したうえで、心理トリガーを活用した効果的なマーケティング施策をご紹介します。
消費者の行動に影響を与える「心理トリガー」とは
心理トリガーとは、人間の意思決定や行動に影響を与える仕掛けのことです。消費者は、何らかの決め手やきっかけがあって商品やサービスを購入しています。その決め手やきっかけを作為的に提供する戦略が心理トリガーです。
心理トリガーがマーケティングで重要視される理由
人間は、何らかの感情の動きに扇動されて商品やサービスを購入するケースが多いです。例えば「数量限定」「先着10名」と記載された商品を見かけると、人間は「売り切れる前に買いたい」「希少な物を購入するチャンスを逃すのはもったいない」といった心理状態に陥るものでしょう。
このような心理状態を理解して、マーケティングに活かすことにより、顧客の購買意欲を引き出しやすくなります。また、プレミアム感を付加できるため、より魅力的な商品やサービスであるように演出できることも、心理トリガーが重要視される理由です。
心理トリガーをマーケティング施策に活かす方法
心理トリガーをマーケティング施策に活用すると、消費者の心理に訴えかけて購買につなげやすくなります。心理学を利用した効果的なマーケティング施策について、具体例を5つ見てみましょう。
<心理トリガーをマーケティング施策に活かす方法>
・ランキングを表示する
・選択肢を増やしすぎない
・単純接触効果を活用する
・口コミやレビューを掲載する
・専門家の力を借りる
ランキングを表示する
「売上ランキング」や「アクセスランキング」は、消費者が参考にすることが多い指標です。多くの人が購入したり、注目したりしている商品に安心感や期待感を覚える人は多く、どの商品を購入するか悩んでいる顧客の背中を押せます。
子どものころに「みんなが持っているから」という理由で買った物があるのではないでしょうか。そのような集団意識を持つのは、大人も同じです。
選択肢を増やしすぎない
選択肢は多くても3~4つまでに抑えましょう。多くの選択肢を用意したほうが顧客にとって有益との考え方もあります。しかし、行動心理学的には、人間が正しく選択できるものは3つ程度までといわれています。
例えば観光地でおみやげを買おうとしているとき、似たような商品が店頭に数十種類も並んでいると、どれを選ぶか悩んでしまうでしょう。選択肢を狭めておけば、急いでいる人でも購入を決断しやすくなり、カートに入れたまま購入されない「カゴ落ち」を防ぐ確率が上がります。
単純接触効果を活用する
単純接触効果とは、ある刺激を繰り返し起こすことによって顧客の好意を生み出す現象です。特に商品購入後やサービス利用後の顧客に対して、アフターフォローなどの形で繰り返し接触すると、自社への好感度が向上しやすくなります。
テレビCMで何度も聴いた曲を自然に覚えて歌ったり、満員電車でいつも同じ車両に乗っている人に親近感を覚えたりした経験はないでしょうか。単純接触効果を活用すると、自社への愛着を深めてもらいやすくなります。
口コミやレビューを掲載する
実際に自社を利用した顧客による口コミやレビューも、顧客が購買の有無を決めるうえで参考にしがちな要素です。ポジティブな口コミが多ければ、顧客に安心や信頼を与えられるため、購買につなげやすくなります。
特にECサイトでは、商品のテストや試食といった形を使って顧客にアピールできません。顧客は「購入して後悔しないだろうか」と考えがちですが、商品の評価が高ければ「多くの人が満足しているし、一度買ってみよう」という気持ちにさせられます。
専門家の力を借りる
専門家による監修を受けたり、インフルエンサーの力を借りて商品を宣伝したりすることにより、商品の説得力が増します。人間は肩書や地位などの権威に影響されやすいといわれており、これをマーケティング施策に活用することも可能です。
聞き覚えのない会社の商品でも、有名なタレントがPRしていると「この人が関わっている商品なら安全だろう」と感じないでしょうか。心理トリガーを上手に活用すると、現時点では知名度が低い企業や商品でも、購買につながりやすくなります。
心理トリガーの代表的な心理効果とその使い方
心理トリガーの代表的な心理効果は次の5つです。ここでは、心理トリガーによる心理効果をどのように使うと効果的なのかについても解説します。
<心理トリガーの代表的な心理効果とその使い方>
・イベント
・希少性
・共通の敵
・会話
・返報性
心理トリガー ①イベント
イベントの発生中、人間は興奮状態に陥りやすいものです。例えばワールドカップ開催期間中に、普段は購入しないサッカー関連グッズを買ったり、飲食店に出かけて盛り上がったりした経験がある方も多いでしょう。
近年は「ブラックフライデー」などのセールも知名度を高めています。イベント中は消費者が財布のひもを緩めやすいため、イベントに便乗してセールを行ったり、キャンペーンを仕掛けたりすると良いでしょう。
心理トリガー ②希少性
「限定販売」「先着10名」「残り5個」のように、商品の希少性を訴える方法も有効です。「早く購入しなければ他の人に取られてしまう」といった焦りが生まれ、いわゆる衝動買いをさせやすくなります。
心理トリガー ③共通の敵
共通の敵がいると、仲間意識が生まれて、親近感を覚えてもらいやすくなります。悪役に立ち向かうヒーローが応援されるのも、観客にとって共通の敵がいるからです。
例えば楽天モバイルは「他社の携帯料金は高すぎる」というキャッチコピーでテレビCMを放送しました。このように共通の敵を批判しながら訴えかけると、消費者に共感されやすくなります。
心理トリガー ④会話
人間は会話を好みやすいため、一方向的にアピールするよりも、双方向的にコミュニケーションを取るほうが効果的です。見込み客と接触する機会を増やしたり、アフターサポートで電話をかけて会話をしたりすると、単純接触効果にも期待できます。
心理トリガー ⑤返報性
自分の得になることをしてもらった場合、何かお返しをしようという気持ちになるものです。日本には年賀状やお歳暮といった「お返し」の文化が浸透している背景から、返報性も重視すると良い心理トリガーのひとつといえます。
例えば「試食」や「試飲」といったサービスは返報性を期待して行う施策でもあります。既存顧客に向けて新商品のサンプルを送るといった施策も有効です。
まとめ
・心理トリガーとは、人間の意思決定や行動に影響を与える仕掛けのことである。
・人間は何らかの感情に扇動されて購買を決断しがちなため、心理トリガーの活用はマーケティング施策において重要視されている。
・代表的な心理トリガーの心理効果には「イベント」「希少性」「共通の敵」などがある。
いかがでしょうか。心理トリガーを活用することにより、消費者の信頼度や期待感を高めたり、自社への愛着を深めたりする効果が期待できます。意図的に消費者を扇動するマーケティング施策を用いて、購買意欲を刺激しましょう。